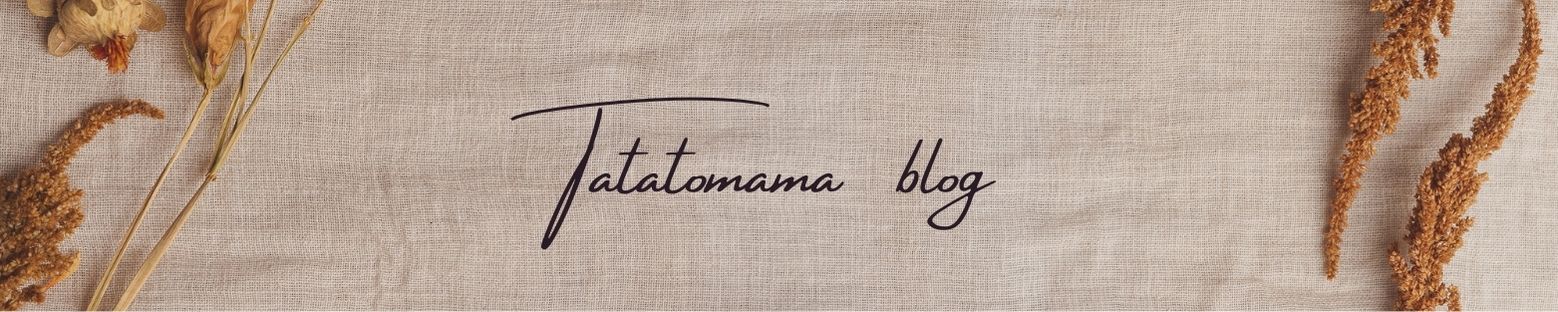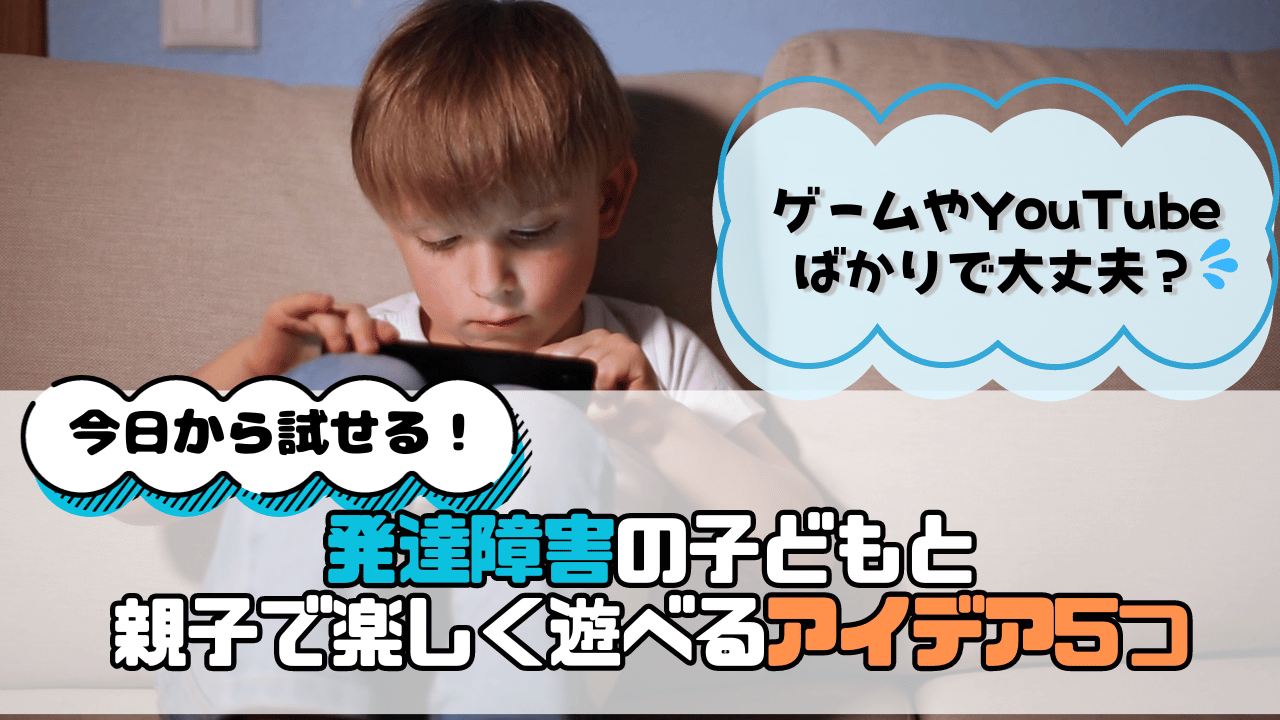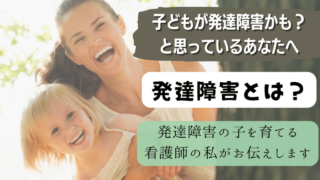発達障害の子におすすめの遊びってどんなの?
自閉症の子どもが、外で遊ばずにゲームやYouTubeばかりで心配……
実は、ASDやADHDの子の場合、ゲームにハマりやすいという特性があります。
また、ゲームをやりすぎは『ゲーム依存』のリスクだけでなく、家にこもることで体力低下や抑うつなど、親としては心配なことばかり。
だからこそ、幼少期では極力ゲームやYoutubeに子守をさせないようにする必要があります。
一番良い方法としては、親が子どもと一緒に遊ぶことで、発達を促すことにつながります。
実際に発達障害児を育てる私が、親子で楽しめるおすすめの遊び、親子で遊ぶメリットをご紹介します!
さらに、ゲームやYoutube依存を卒業し、発達を促す効果も期待できるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
【発達障害】おすすめの親子遊びアイデア5選

ずばり、発達障害の子におすすめの親子遊びアイデアは以下の5つです。
- 絵本、おままごと
- 運動遊び
- ものづくり
- 料理
- 自然遊び
様々な特性や性格がありますので、お子さんに合った方法をお試しくださいね。
うちの子の場合は、最後の自然遊びが一番好きです!
あなたのお子さんは、どんな遊びを気に入りそうですか?
ぜひチェックしてみてくださいね♪
絵本、おままごと

きっとあなたも『絵本の読み聞かせは大切』と、どこかで聞いたことがありますよね。
その理由は、絵本は創造力や感性、共感性を豊かにしてくれるからです。
さらに、ことばを覚えたり、視覚と聴覚の刺激により、脳の成長を促すことができます。
発達障害のある子には、視覚や聴覚が優位などの特性があるのをご存知ですか?
その特性からも、『見る』『聞く』ことで想像力を育てられるので、絵本の読み聞かせは発達障害と相性抜群。
なかなか静かに聞いてくれなくても、繰り返し読み聞かせてみましょう。
絵本が、親子の大切なコミュニケーションとなり、子どもの情緒を安定させてくれますよ。
また、おままごとやごっこ遊びも、共感性を育てられるので、発達障害の子におすすめの遊びです。
長男の主治医から、子どもと対面し共感性を育む遊びを取り入れるように言われ、絵本の読みかせやごっこ遊びを意識して取り入れました!
運動遊び

実は、運動は心の健康、生活の質の向上に不可欠だということをご存知ですか?
それは子どもにとっても例外ではなく、運動は全身の発達においてとても重要です。
しかし、運動は好きな子もいれば、苦手な子もいますよね。
ちなみに、うちの子も体幹力が弱く運動は苦手なのですが、遊びの中で体を動かすのは大好き。
だから、運動といっても、親子で鬼ごっこやボール遊びなどをするだけでOK!
また、屋外に限らず、室内で運動遊びを取り入れる方法もありますよ。
例えば、しっぽとりやタオルキャッチゲームなど、自宅でも気軽に行うことができますね。
我が家も利用した、発達障害の子のための自宅で楽しく遊びながら体幹を鍛えられるオンライン運動教室もおすすめ。
親子にとってメリットたくさん!のへやすぽアシストですが、今なら無料で体験できるので、気になる方はコチラをどうぞ。
また、へやすぽアシストの体験レビューはこちらの記事を参考にしてみてくださいね。
ものづくり

お絵かき、積み木、段ボールなどを使った工作など、ものづくりもおすすめです。
ものづくりには、子どもに自由に創造する楽しさを教えてくれます。
さらに創作活動を通して、手指や道具の使い方を学び、五感を刺激し、脳を活性化します。
また、積み木は見本を模倣することや、色・形・言葉の認識を鍛えることもできます。
料理

発達障害の子と遊びの一環として料理をすることもおすすめです!
料理をすると、手先を鍛えるだけでなく、手順を組み立てる能力が育ちます。
また、失敗した時の行動を見せることで、対処のしかたを学ぶ良い経験になるためです。
例えば、卵を割って殻が入ってしまったらどうすればいいのか?
牛乳や小麦粉をこぼしてしまったら、どうするのか?など……
ただし、料理は安全に配慮して行いましょう。
子ども包丁を用意したり、火や刃物を使わないか大人が必ず代わりに行ったりすると安心でしょう。
自然遊び

自然の中には、子どもの感覚を刺激するものがたくさん転がっています。
いきもの探し、どんぐり集め、落ちている木を集めてたき火ごっこなど……
外が苦手な子でも、きっと興味を示すものが何かしらあるはず!
自然と体を動かし、五感を刺激し、想像力を豊かにしてくれるので、自然遊びは発達障害の子におすすめです。
また、親にとっても緑に癒されたり、子どものたくましい一面が見られたりします。
ぜひ、週末は自然あふれる公園へお出かけしてみてはいかがでしょうか?
発達障害の子が親と遊ぶメリットとは?

発達障害のある子におすすめの親子遊びを知ったら、親子で遊ぶメリットも把握しておきましょう!
さて、親子で一緒に遊ぶことによってどんな良い効果があるのでしょうか?
- 愛着形成や共感性を育てられる
- 感覚や脳の発達を促せる
- 運動能力を効率的に高められる
ひとつずつ、みていきましょう。
愛着形成や共感性を育てられる

まず第一に、遊びを通して親子でふれあうことで、愛着形成ができます。
愛着形成は情緒を安定させ、自己肯定感を高められるので、子どもにとって非常に大切。
また、ごっこ遊びやだれかと楽しい体験を共にすることで、共感力を高められます。
ASDやADHDの場合は、子どものためにもなるべく共感性は育ててあげたいですよね。
ぜひ、積極的に親子で遊ぶようにしてみましょう。
感覚や脳の発達を促せる

まず、子どもの人生を明るく彩るためには、感性豊かに育てることが大切です。
そして、脳や感覚器官の発達を助けるためには、子どもの五感への刺激です。
よって、視覚的、聴覚的、あるいは感触や匂いなど、感覚器官に訴える遊びを意識しましょう。
親子での触れ合いも、自然と子どもの五感を刺激することができるのでおすすめです。
運動能力を効率よく高められる

実は、発達障害のある子どもには、体幹力が弱い子が多いです。
そして、体幹が弱いと、集中力が続かない、ケガをしやすいなど日常生活に支障が出ることも。
詳しくは、以下の記事を参考になさってみてください。
つまり、体を動かすことは、楽しみながら運動能力を高められるため、発達障害の子におすすめの遊びなのです。
発達障害の子におすすめの遊びで成長発達を促そう!
親と一緒に楽しく遊べる発達障害児におすすめの遊びは、以下の5つです。
- 絵本、おままごと
- 運動遊び
- ものづくり
- 料理
- 自然遊び
そして、発達障害のある子どもと親が一緒に遊ぶメリットはこちらです。
- 愛着形成や共感性を育てられる
- 感覚や脳の発達を促せる
- 運動能力を効率的に高められる
まずは、その子の特性や性格に合った方法で、親子で楽しく遊びましょう!
それは、楽しい経験であるとともに、子どもの成長・発達を促すための大切なエッセンス。
ゲームやYoutubeばかりにならないよう、発達障害の子にはぜひここで紹介したおすすめの遊びを親から提案してみてください!
何よりもお互いにとって、幸せなひとときであり、ステキな思い出になりますよ♪
最後までお読みくださり、ありがとうございました。